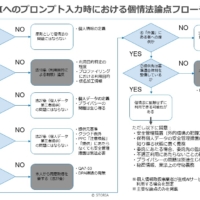ベンチャー企業法務 スタートアップ
【スタートアップ資本政策連載・第6回】 プロダクト開発と知的財産権
*本記事は「【連載】ストーリーを通じて学ぶスタートアップのための資本政策と資金調達手法」の第6回目の記事です。
第6回「プロダクト開発と知的財産権」では、スタートアップが開発するプロダクトに関連する知的財産権の取り扱いについて解説します。スタートアップがプロダクトやサービスを開発する過程では、ハードウェアの場合には特許権及び著作権、ソフトウェアの場合には著作権を中心とした様々な知的成果が生み出されますが、これは誰のものなのでしょうか。また、スタートアップが知的財産権を事業で効果的に利用するためには、どのような制度設計や契約が必要なのでしょうか。
Emotechでは、装着者の心理状態をモニタリングする時計型のウェアラブルデバイスを開発することを目標に研究開発を進めています。川崎さんの友達にもウェアラブルデバイスの設計や内部プログラムの開発を手伝ってもらっているようですが…
Contents
事業で生じた知的財産権の帰属
藤本「川崎さんの友達のエンジニアに、開発作業を手伝ってもらっているということだったね。そのエンジニアとEmotechとの間で契約書は作っているかな」
川崎「いえ、現状は口頭でお願いして手伝ってもらっているだけです。友達付き合いも長いので、改めて契約という感じにもならなくて」
藤本「なるほど。ただ、会社で成果を利用するにあたっては、生み出された成果の取り扱いについてはきちんと決めておく必要があるね。今回は従業員ではなく外部のエンジニアだから、業務委託契約書を今からでも作って、知的財産権がEmotechに帰属するように合意すべきだね」
原則:作った人に知的財産権が帰属する
スタートアップの事業活動において生じた技術的成果には、知的財産権が発生する場合があります。たとえば、プログラムコードやウェブサイトのコードの具体的な記載が独創的なものである場合には著作権が発生しますし、先行技術と比較して新規性や進歩性を有しているものについては特許を取得できる可能性があります。
このような成果の知的財産権は、成果を作った人に帰属するのが法律上の原則です。これは、業務委託などで技術的成果の作成を依頼した場合でも同じです。つまり、お金を出して技術的成果の開発を依頼しただけでは、当該技術的成果の知的財産権は、作った人(受託者)が持っていることになります。これは、会社が当該技術的成果を利用しようとするたびに、受託者の許諾を要するということを意味します。ビジネスで技術的成果を利用するにあたっては、非常に使い勝手が悪い条件です。
どうするか→契約で会社に知的財産権を帰属させる
「業務委託での技術的成果が、スタートアップで自由に使えない」という事態を防ぐため、以来の際には業務委託契約書を必ず作成することをおすすめします。
- 業務委託契約書の中で、「委託業務により生じた知的財産権は、委託者に帰属する」旨の条項を記載します。具体的には、以下のような条項です。
本業務の成果物に関する知的財産権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む。以下同じ)及び本業務の過程で生じた一切の知的財産権は、委託者に帰属する。
- 知的財産権の帰属だけでなく、委託料の額や支払時期、損害賠償の定め等を合意すると、トラブルを防止できるだけでなく、万が一トラブルに発展してしまった際にもダメージを最小限にすることができます。
上記のような業務委託契約書が締結できていれば、業務委託により生じた技術的成果の知的財産権はスタートアップに帰属することになり、当該技術的成果は、会社が自由に利用することができます。
業務委託契約書(スタートアップ・外部技術者間)の雛形を作成しましたので、活用いただければ幸いです。
従業員が作った知的財産権の帰属:職務発明規程
大山「従業員を雇った場合、その従業員が知的財産権を作る場合もありますよね。その取扱はどうなりますか」
佐々木「えっ、当然会社のものだと思ってたけど、違うのかな」
藤本「従業員の場合も、外部技術者に委託する場合と同様に、規程を整備して対応することが必要だね」
スタートアップが従業員を雇用した際には、当該従業員が業務として作成した技術的成果の取り扱いにも注意する必要があります。
業務上作成された技術的成果の著作権については、特別な契約の定めがない限り会社に帰属します(著作権法15条2項)ので、特段の手当をしていなくても問題ありません。
一方で、特許権については、従業員が所属する会社ではなく、発明を行った従業員個人に帰属するのが法律上の原則です(特許法35条1項)ので、特段の手当をしていない場合、発明の権利は従業員に帰属してしまいます。
業務上開発された発明の特許権を会社に帰属させるためには、「職務発明規程」という内部規程を作成することが必要です。「職務発明規程」の中では、従業員が職務上作成した発明(職務発明)の権利が会社に帰属することに加え、当該職務発明の権利を取得する対価(法律上は、「相応の利益」と呼ばれます)として従業員にどの程度の金額を支払うかを記載する必要があります。
職務発明規程の雛形については、特許庁において「中小企業向け職務発明規程雛形」が公開されており、スタートアップにおいても参考となると考えられますので、ご参照ください。
ノウハウ・アイデアについて
具体的な成果になる前段階のもの、たとえば、事業上のノウハウ、プログラムコードの前提となるアルゴリズムの構想、事業のアイデアなどについては、そのままでは知的財産権が発生しないケースがほとんどです。
このようなノウハウ・アイデアについては、無関係の第三者に漏れないような手当を講じる必要があります。具体的には、
- ノウハウ・アイデアに触れる人を限定し、むやみに無関係の第三者に開示しない。
- 業務委託先等にノウハウ・アイデアを開示する場合には、開示する前に、当該ノウハウ・アイデアを「秘密情報」として保護する内容の契約(秘密保持契約)を必ず締結する。
ことが必要です。
事業で他者の知的財産権を利用する
藤本「他に事業で利用する知的財産権はあるかな」
川崎「私が大学の研究室にいた頃に研究していたテーマが、ウェアラブルデバイスに応用できそうなんです。特許も取得しています」
藤本「なるほど、それなら、大学との間でその特許のライセンス契約を締結する必要があるね」
大山「えっ、川崎さんが研究していたものなのに、川崎さんは何の権利も持っていないんですか」
藤本「実はそうなんだ。誤解している人も多いから、丁寧に説明するよ」
他者知財の利用-ライセンス(利用許諾)
スタートアップ以外の第三者(個人の場合も、法人の場合もありえます)が、事業に必要な技術の知的財産権を保有しているケースがあります。この技術を利用したい場合には、当該第三者から、知的財産権のライセンス(利用許諾)を受ける必要があります。
ライセンス契約においては、主に以下のような事項が規定されます。なお、知的財産権を保有しておりライセンスをする側の当事者を「ライセンサー」、ライセンスを受ける側の当事者を「ライセンシー」といいます。
- ライセンス対象(どの技術的成果のライセンスを受けるか)
- ライセンスの範囲(どのような目的で、どのような事業でライセンスを利用するか)
- ライセンスの対価(ライセンスを受ける対価としてどのような対価を支払うか)
- 監査(ライセンス料が正しく計算されているかライセンサーが監査する)
特にライセンスの対価については、その算定・支払方法にいくつかバリエーションがあります。具体的には、以下のようなものです。
- ランニングロイヤリティ方式:製造した製品の製造費用あるいは販売価格に一定のパーセンテージを乗じて算定された額をライセンス料とする
- 一括払方式:あらかじめ決められた額を契約締結時に一括で支払う
- イニシャルフィー+ランニングロイヤリティ併用方式:契約締結時に一部の金額を支払い、契約締結以後はランニングロイヤリティ方式で算定された額をライセンス料とする。
大学・TLOとのライセンス契約(大学発スタートアップ)
大学で研究をしていた研究者の方がスタートアップに参画する場合、大学所属時代の研究成果は、職務発明として大学に帰属していることがほとんどです。つまり、大学時代に携わっていた研究成果をスタートアップにおいて利用したい場合には、大学との間でライセンス契約を締結する必要があります。
また、一部の大学では、大学が保有する技術や研究成果を民間に還元する(対価として、大学はライセンス料を受取り、さらなる研究開発に投資する)ための特別の機関として、TLO(Technology Licensing Organization)という機関を保有しています。TLOが存在しているケースでは、当該大学のTLOとの間でライセンス契約の交渉を行うことになります。
大学とのライセンス契約については、次回記事で詳しく解説します。